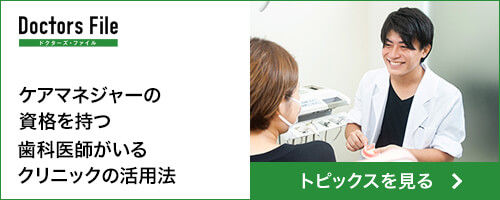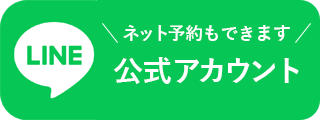コラム COLUMN
小児の歯軋りとは?
院長の馬場です。
そもそも歯ぎしりはなぜ起こるのか?
 歯ぎしりの原因として皆様が想像されるのは「ストレス」だと思います。
歯ぎしりの原因として皆様が想像されるのは「ストレス」だと思います。
しかし、ストレスだけではなく、噛み合わせの微妙な変化や顎関節と歯のバランスなど、物理的な面でも歯ぎしりは起こります。
さらには睡眠の質にも左右され、深い睡眠状態を意味する「ノンレム睡眠」時には歯ぎしりは起こらないとも言われています。
歯ぎしりの種類
一言に歯ぎしりと言っても大きくわけて3種類ございます。
子供の歯ぎしりだけでなく、大人の歯ぎしりもこれに属します。
グラインディング
上下の歯を強く擦り合わせる、最も多い歯ぎしりです。
歯を強くこすり合わせる行為なので、歯の摩耗が激しいです。
クレンチング
上下の歯で強く噛みしめたままの、音の出ない歯ぎしりです。
昼夜関係なく行っているもので、音が出ないので周りからの指摘もなく、気付きにくいのが特徴です。
タッピング
上下の歯をぶつけ合って音を出すものです。カチカチと音を出すのが特徴です。
歯ぎしりが長期間続くと、歯や歯の根っこが割れてしまい、そこから細菌が侵入し神経が死んでしまったり、知覚過敏の原因となり歯がしみる他、顎関節症になり顎に痛みが出る恐れがあるなど様々な悪影響があります。
歯ぎしりは大人だけのものではない
結論から申し上げると、5歳~10歳の子供の約4割が歯ぎしりをしているという説があります。
ですので、お子さんの歯ぎしりで悩んでいる親御さんは一旦ご安心ください。
では、子供が歯ぎしりをするのは何故でしょうか。
大人と同様に、子供は子供なりのストレスを抱えているのでしょうか。
実は、無意識に「噛み合わせを整えている」と言われています。
子供の歯ぎしりの多くは5歳~10歳の間に多く起こるという見識が広く理解されています。
この時期というのは、乳歯(子供の歯)から永久歯(大人の歯)に生え変わる時期です。
この頃の子供は身体の成長に伴って、顎の骨格も大きく成長していきます。
すると、乳歯と乳歯の間に隙間ができてきます。
そうすると噛み合わせが悪くなるため、無意識のうちに噛みやすい位置に調整をする意味で歯ぎしりをしています。
さらに、永久歯が生えるためのスペースを作っているので、この時期の歯ぎしりは、お口の中が正しい状態で成長をするために行うものです。
乳児がする歯ぎしり
 乳歯から永久歯への生え変わりの時期に歯ぎしりを行う他にも、乳歯が生えたばかりの赤ちゃんも歯ぎしりをします。
乳歯から永久歯への生え変わりの時期に歯ぎしりを行う他にも、乳歯が生えたばかりの赤ちゃんも歯ぎしりをします。
歯ぎしりの音の大きさに驚いた親御さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
実はこれも子供(5歳~10歳)と同様に、意味のある行為です。
赤ちゃんは、およそ6ヶ月頃から下の歯が生えてきます。
その後、上の歯が生えてきたタイミングで歯ぎしりをする赤ちゃんが多いです。
これは「顎の位置を調節している行為」です。
詳しく説明すると、成長の過程において歯が生えていない赤ちゃんは、食事という行為に対して「吸う」という動作を主に行っています。
この動作は顎の動きにおいてとても単純な動きをします。
その後の成長過程で歯が生えてくると、ものを食べる際に「吸う」動作から「噛む」動作に変わります。
噛む動作は上下左右に顎を動かすため、想像される以上に複雑な動きをします。
そこで、吸う時に使う顎の位置を噛む時に使う顎の位置に調整が必要になってきます。
その時に行うのが歯ぎしりです。
赤ちゃんの歯ぎしりは噛むことのできる「顎の位置の調節」をしているのです。
著者紹介
馬場 達也(ばば たつや)

「もし自分が患者様の立場だったら......」
私は診療中に、何度もこの言葉を自分自身に問いかけています。自分が目の前の患者様なら、どんな治療を受けたいだろうか。こんな説明で納得できるだろうか。
このような自問自答を繰り返しながら、丁寧な治療やわかりやすい説明を心がけてきました。
とくに患者様の痛みにはしっかり寄り添いたいと考え、可能な限り治療の痛みを軽減するためにあらゆる工夫をしています。
また、治療前後の画像をお見せして共に回復を喜び合ったり、疑問があればすぐにお答えしたりと、患者様との人間同士の関係を大切にしてきました。
もちろん患者様に信頼していただくため、治療技術を高めるための努力も惜しみません。
『一時的』ではなく『一生涯』の担当医として、皆様に寄り添えたらという思いで日々診療にあたっています。【本八幡TaCファミリー歯科】をどうぞよろしくお願いいたします。
- 経歴
- ・昭和大学歯学部 卒業
・日本歯科大学附属病院 研修
・町田駅前グレイス歯科矯正歯科 勤務
・けやき歯科 勤務
・本八幡TaCファミリー歯科 開院 - 所属
- ・歯科医師
・ファイナンシャルプランナー 2級
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・日本口腔インプラント学会 所属
・インビザライン(マウスピース)矯正認定医 - サーティフィケイト
- ・総合インプラント研修センター100時間コース受講